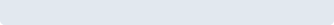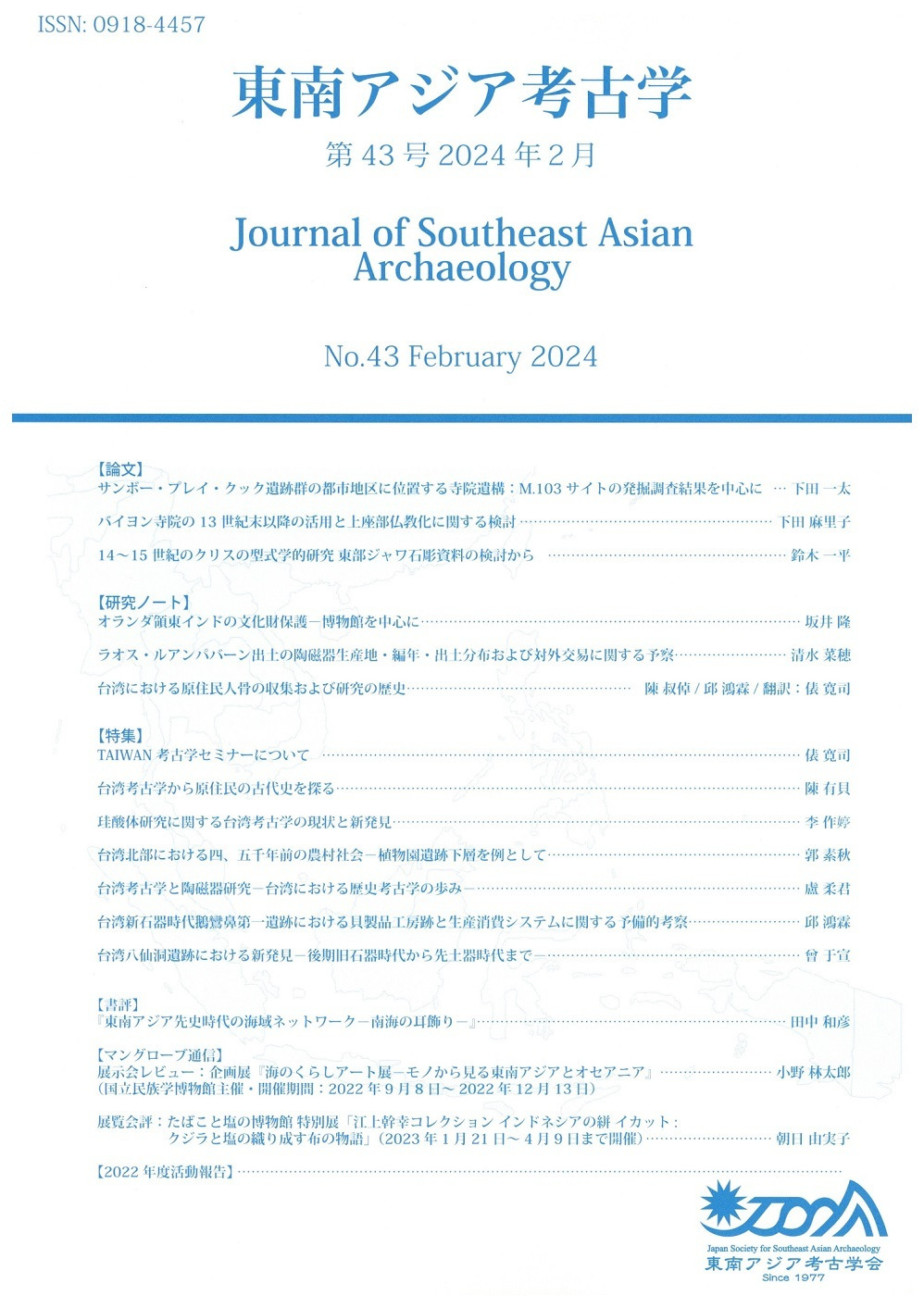『東南アジア考古学』第43号(2024年2月刊行)掲載原稿概要一覧
| 種別 | 論文 |
| タイトル | サンボー・プレイ・クック遺跡群の都市地区に位置する寺院遺構:M.103サイトの発掘調査結果を中心に |
| 著者 | 下田 一太(筑波大学)、チャン・ヴィタロン(サンボー・プレイ・クック国立機構) |
| 掲載ページ | 5-22 |
| 要旨 | 前アンコール時代の真臘の王都、イーシャーナプラに比定されるサンボー・プレイ・クック遺跡群の西側を占める都市地区内には、煉瓦やラテライト遺構を含む86サイトと多数の溜池の分布に加えて、格子状地割を形成した水路遺構の配置が推定され、計画的な都市構造の様相が解明されつつある。複数の祠堂によって構成された複合的な寺院も多数認められており、M.103サイトは三基の祠堂と周壁、溜池により構成されるこうした複合寺院の一つである。このサイトにおける考古学的発掘調査の結果、異なる平面形式で時代差が推測される装飾リンテルを有する二基の祠堂が確認され、また周壁においては正面の東門が不在である一方、南北辺には異なる形式の門が配置されており、同時期の一般的な寺院の構成からは逸脱する特徴が認められた。都市地区における寺院の伽藍構成や建造時期を考察する上で、本サイトにおける調査結果は示唆に富むものであった。 |
| キーワード | カンボジア、前アンコール時代、イーシャーナプラ、都市構造、クメール寺院 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 論文 |
| タイトル | バイヨン寺院の13世紀末以降の活用と上座部仏教化に関する検討 |
| 著者 | 下田 麻里子(早稲田大学文学研究科) |
| 掲載ページ | 23-40 |
| 要旨 | バイヨン寺院の増改築過程は4段階変遷説が通説とされるが、ジャヤヴァルマン7 世の治世後の増改築はすべて同一の建造段階にまとめられ、特に13世紀末以降のバイヨン寺院およびその周縁部における建設活動は不鮮明である。本稿では上座部仏教の導入とともにバイヨン寺院の周辺に建造されたと考えられる周壁と周囲の上座部仏教に関連する衛星寺院遺構群に着目し、13世紀末以降のバイヨン寺院とその周縁部における上座部仏教化の実態解明を目的とする。そのために、遺構の現状調査とフランス極東学院による20世紀初頭の整備時の資料を手掛かりに、衛星寺院遺構の形態や配置の復元考察を試みた。その上で、周壁や衛星寺院遺構の建造順序、時期やその意図について考察することで、バイヨン寺院の上座部仏教化開始の時期や、複数の段階を経て、衛星寺院を含めた複合的な信仰の場として変容していった様相について言及した。 |
| キーワード | カンボジア、バイヨン、上座部仏教、仏教基壇、周壁 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 論文 |
| タイトル | 14~15世紀のクリスの型式学的研究 東部ジャワ石彫資料の検討から |
| 著者 | 鈴木 一平(総合研究大学院大学) |
| 掲載ページ | 41-59 |
| 要旨 | 鍛造製鉄剣“クリス(Keris)”は東南アジア島嶼部地域を代表する物質文化であるが、年代基準となる資料の不足により16世紀末以前の様相は殆ど知られていない。本論文では、クリスの図像が登場する14~15世紀(東部ジャワ時代後期)の石彫資料7点を対象に、史料批判を加えた上でクリス図像の分析をおこなうことで、16世紀末以前のクリスの形態的特徴を明らかにする。分析の結果、図像に見えるクリス形態に16世紀末期以降のクリスとの連続性が見出された一方、鞘上部や鞘尻など部分的に独特の造形が確認され、当該時期のクリスの形態的特徴として指摘された。 |
| キーワード | クリス、石彫、図像、東部ジャワ時代 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 研究ノート |
| タイトル | オランダ領東インドの文化財保護−博物館を中心に |
| 著者 | 坂井 隆(NPO法人 アジア文化財協力協会) |
| 掲載ページ | 63-80 |
| 要旨 | 18世紀後半にアジアで最も早く設立された博物館であるバタヴィア協会博物館を持つオランダ領東インドでの文化財保護活動の推移について、次の時代に分けて現地保存原則と地元民関与の視点で博物館などの果たした役割を中心に検討する。 前期(1778年~1913年頃):協会博物館時代 後期(1913年頃~1942年):考古局設立とスマラン植民地博覧会の影響 特に後期の地元民を含む研究保護活動活発化に焦点を当て、植民地博覧会開催を契機とする東部ジャワとスマトラ島アチェでの地域博物館設立の経緯と目的を考える。さらに文化財の現地保存の実態については、考古局の1923年でのジャワとマドゥラの遺跡・遺物目錄から具体的に検証する。 |
| キーワード | バタヴィア協会博物館、オランダ領東インド考古局、スマラン植民地博覧会、モジョクルト博物館、アチェ博物館 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 研究ノート |
| タイトル | ラオス・ルアンパバーン出土の陶磁器生産地・編年・出土分布および対外交易に関する予察 |
| 著者 | 清水 菜穂(Independent Researcher/ラオス国立博物館)、Joyce White(東南アジア考古学研究所)、Marie-Claude Boileau(ペンシルベニア大学考古・人類学博物館)、Bounheuang Bouasisengpaseuth(前ラオス国立博物館)、Thonglith Luangkhot(ラオス情報・文化・観光省遺産局)、Souliya Bounxaythip(ラオス情報・文化・観光省遺産局) |
| 掲載ページ | 81-98 |
| 要旨 | ラオス北西部に位置するルアンパバーン県では、Institute for Southeast Asian Archaeologyが考古学調査を継続しており、膨大な量の遺物が出土ないし採集されている。遺物の主体は先史時代の土器類だが、一部資料は歴史時代に帰属する。2022年、既往全調査で収集された遺物の分類作業を実施した結果、歴史時代の陶片資料は在地産の陶器(炻器類)と国外から搬入された、いわゆる貿易陶磁と同定された。小稿では資料の出土様相(組成・製作年代・生産地)を明らかにするとともに、年代的出土傾向・出土分布・搬入経路の検証を通じて当地における対外交易の変容とその背景を探る。 |
| キーワード | ルアンパバーン、炻器(陶器)、磁器、貿易陶磁、ラーンサーン王国 |
| 掲載言語 | 英語 |
| 種別 | 研究ノート |
| タイトル | 台湾における原住民人骨の収集および研究の歴史 |
| 著者 | 陳 叔倬(国立自然科学博物館)、邱 鴻霖(国立清華大学)、翻訳:俵 寛司(国立台湾大学) |
| 掲載ページ | 99-113 |
| 要旨 | 本稿は、台湾原住民(先住民)の人骨の収集に関する研究史に焦点を当て、主に文献調査に基づいて、形質人類学者・民族学者・考古学者による台湾原住民の人骨に関する収集および研究の歴史を紹介しつつ、それら人骨資料の現在の所蔵場所と数量についての概要を明らかにすることを目的とする。日本統治時代の初期に台湾本島の医学校が設立される以前、台湾の原住民の人骨はかなりの数収集されていたことが確認できる。最大の収蔵機関は東京帝国大学であり、合計約40例である。1918年に台湾総督府医学専門学校が設立され、その後台北帝国大学医学部が設立されたことで、台湾原住民の人骨が台湾に保管されるようになった。その中で台湾大学の収蔵が最も多く、全部で207例が記録され、145例がタイヤル族、ブヌン族が46例、ヤミ族が10例、パイワン族が6例であり、これらに関する出所は関連文献に記載されている。今日、原住民人骨の返還は社会的コンセンサスとなりつつある。本稿がそれら活動に対して有益な情報となることを願っている。なお、本稿で対象とする台湾原住民の人骨は19世紀以降に死亡したものであることを明記する。 |
| キーワード | 台湾原住民、人骨、形質人類学、返還運動、日本統治時代 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 特集 |
| タイトル | TAIWAN考古学セミナーについて |
| 著者 | 俵 寛司(国立台湾大学) |
| 掲載ページ | 117-120 |
| 要旨 | 台湾は日本および東南アジアの考古学にとって歴史的に深いつながりがある地域である。東南アジア考古学会においても、会設立当初から台湾とつながりの深い研究者たちや日本への留学経験者などを中心として活発な交流が図られてきた。その流れを受け、2022年度に本学会と台湾の交流企画として、学会員および一般向けに台湾考古学をテーマとするオンラインでの連続セミナー(日本語)「TAIWAN考古学セミナー・シリーズ《台湾考古学の新視点》」を2022年10月から2023年3月にかけて合計6回開催した。本特集はそれらの研究報告である。 |
| キーワード | 台湾考古学、東南アジア考古学会、日本語、オンライン、連続セミナー |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 特集 |
| タイトル | 台湾考古学から原住民の古代史を探る |
| 著者 | 陳 有貝(国立台湾大学) |
| 掲載ページ | 121-125 |
| 要旨 | 台湾の先史時代の遺跡のほとんどは、原住民の祖先が残したものと認識されている。ゆえに考古学はそれら原住民の古代史の探究を可能とする学問である。1980年代以降の台湾では大規模な緊急発掘が増加し、より多くの実物資料が地下から明らかとなり、原住民の古代史の解明を追求する研究者たちにとって、豊かなデータと様々な研究テーマを提供している。そうした研究の中でも「オーストロネシア語族の起源地」や「族」の問題は、研究者だけではなく一般の国民からも重要視されており、今後もそれらに関する研究の成果がますます増えていくことが期待できる。 |
| キーワード | 台湾考古学、先史時代、原住民、「オーストロネシア語族の起源」、「族の形成」 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 特集 |
| タイトル | 珪酸体研究に関する台湾考古学の現状と新発見 |
| 著者 | 李 作婷(国立自然科学博物館) |
| 掲載ページ | 127-131 |
| 要旨 | 台湾における珪酸体研究法の展開は、先史時代の穀物の起源への関心から始まったといえる。現在では珪酸体研究が発展し、材料分析において土壌や土器から珪酸体を分離することが可能である。現在までの成果から、台湾のほとんどの遺跡において珪酸体が検出できることが示され、それらの年代は、早いもので25,000年前、遅いもので500年前である。イネ科における機動細胞の珪酸体を注目する以外に、他の植物由来の珪酸体も注目される。それらの研究は、先史時代の環境復元や穀物の起源などの研究において、重要な進展をもたらしている。 |
| キーワード | 珪酸体、イネ科、機動細胞、環境復元、先史穀物 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 特集 |
| タイトル | 台湾北部における四、五千年前の農村社会−植物園遺跡下層を例として |
| 著者 | 郭 素秋(中央研究院) |
| 掲載ページ | 133-142 |
| 要旨 | 本稿では、2015~2018年、台北市植物園遺跡下層より検出された灰坑の農作物と植物のフローティング・サンプルの分析に焦点を当て、それらに伴い出土する土器や石器、および地質ボーリングの結果と組み合わせ、4、5千年前の先史時代の農村生活の様相について新たな考察を試みる。4~5千年前の台湾北部の新石器時代には、イネとアワの並作(混作)の生業経済モデルがすでに出現しており、定住型の集落と細かな集落の空間配置が出現している。植物園遺跡下層のイネの源流は、長江中流域から江西地域を経由し福建地域へに到達した後、さらに福建から船に乗って台湾海峡を越え、淡水河に沿って台北盆地中央の植物園一帯へと到達した可能性がある。 |
| キーワード | 農村生活、イネ・アワ並作(混作)、大坌坑時期、訊塘埔前期文化、植物園遺跡下層 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 特集 |
| タイトル | 台湾考古学と陶磁器研究−台湾における歴史考古学の歩み− |
| 著者 | 盧 柔君(国立台湾大学) |
| 掲載ページ | 143-150 |
| 要旨 | 台湾考古学は、19世紀末に日本人学者により台湾での考古学活動が開始されてから、常に先史時代に重点をおくものであった。一方、20世紀末より、先住民研究(現在原住民族研究と称す)が注目されはじめると同時に、いわゆる歴史考古学への関心も徐々に高まりを見せるようになった。歴史文献への登場が遅い台湾の歴史考古学は、原住民族の歴史との強い関連性を持ち、また、植民地における多民族の接触・衝突が重要な研究テーマとなっているため、他の東アジア諸国と本質的に異なるところがある。さらに、そこから生み出された議論への焦点も違ってくる。そうした中でも陶磁器は歴史考古学における研究材料としてもっとも代表的なものといえる。台湾の歴史考古学の発展過程において、陶磁器に関する研究方法の変遷を通観しながら、今後の展望として消費研究としての在り方を提示したい。 |
| キーワード | 台湾考古学、歴史考古学、原住民族、陶磁器、消費研究 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 特集 |
| タイトル | 台湾新石器時代鵝鸞鼻第一遺跡における貝製品工房跡と生産消費システムに関する予備的考察 |
| 著者 | 邱 鴻霖(國立清華大学) |
| 掲載ページ | 151-153 |
| 要旨 | 鵝鸞鼻第一遺跡の貝製品工房跡は、台湾の南端部に位置する大規模遺跡であり、帰属年代は4千年前と古く、土器や玉石器、骨角器、貝製品などの遺物の出土に加え、石棺や貝塚、炉跡などの遺構が検出されている。中でも貝製品に関する出土資料が最も重要である。4千年前は先史オーストロネシア語族の移動・拡散が最も活発に行われた時期と考えられ、貝器(貝製品)を有する文化は、その重要な特徴の一つとされている。したがって今回の資料は、従来認められなかった貝製品の生産/加工と消費システムを解明する証拠となる。さらに、琉球列島や東南アジア、太平洋諸島との比較により、新たな研究視野や研究テーマが生まれることが期待される。 |
| キーワード | 鵝鸞鼻第一遺跡、貝製品工房跡、生産消費システム、台湾、新石器時代 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 特集 |
| タイトル | 台湾八仙洞遺跡における新発見−後期旧石器時代から先土器時代まで− |
| 著者 | 曾 于宣(国立台湾史前文化博物館) |
| 掲載ページ | 155-160 |
| 要旨 | 八仙洞遺跡は、台湾東海岸の海食洞穴群に位置する台湾旧石器時代の代表的な遺跡で、放射性炭素年代測定によれば、30000~15000BPの範囲で人間が活動していたことが確認されている。本遺跡における最初の発掘調査は、1968~1970年に国立台湾大学の地質学科及び考古人類学科から編成された「八仙洞考古発掘隊」により行われたものである。それからおよそ40年を経て、2008~2015年に中央研究院歴史言語研究所の臧振華らによる4年度にわたる研究計画が実施された。その後積み重ねられた研究の成果として、台湾後期旧石器時代と先土器時代の関係性や年代、石器製作技術など、当該遺跡における考古学的文化の様相が明らかになった。 |
| キーワード | 八仙洞、長濱文化、旧石器時代、先土器時代、石器製作技法 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 書評 |
| タイトル | 『東南アジア先史時代の海域ネットワーク−南海の耳飾り−』深山絵実梨著、2021年 |
| 著者 | 田中 和彦(鶴見大学) |
| 掲載ページ | 163-166 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | マングローブ通信 |
| タイトル | 展示会レビュー:企画展『海のくらしアート展−モノから見る東南アジアとオセアニア』(国立民族学博物館主催・開催期間:2022年9月8日~2022年12月13日) |
| 著者 | 小野 林太郎(国立民族博博物館) |
| 掲載ページ | 167-170 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | マングローブ通信 |
| タイトル | 展覧会評:たばこと塩の博物館 特別展「江上幹幸コレクション インドネシアの絣 イカット:クジラと塩の織り成す布の物語」[2023年1月21日~4月9日まで開催] |
| 著者 | 朝日 由実子(日本女子大学) |
| 掲載ページ | 171-174 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |