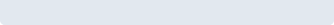『東南アジア考古学』第42号(2023年2月刊行)掲載原稿概要一覧
| 種別 | 論文 |
| タイトル | ミャンマー産陶器の化学分析 |
| 著者 | 佐藤 由似(奈良文化財研究所)、田村 朋美(奈良文化財研究所) |
| 掲載ページ | 5-23 |
| 要旨 | 14~17世紀のミャンマーと日本で出土したミャンマー産陶器のX線分析および鉛同位体比分析を実施した。分析の結果、白釉と緑釉は鉛釉であり、白釉は錫石(SnO2)によって白濁していることが分かった。一方、黒釉はカルシウムの多いアルカリ釉であった。アラカン地方ではコバルトで着色されたアルカリ釉の藍釉陶器が確認された。鉛釉の鉛同位体比分析を実施した結果、先行研究でタイのソントー鉱山の鉛が使用されたと考えられているN領域に一致した。一方、新たに入手したミャンマーの鉛鉱石も同じくN領域の鉛同位体比を持つことが分かった。ミャンマー産陶器生産に使用された鉛原料産地はタイだけでなく、ミャンマーにも存在する可能性が示された。 |
| キーワード | ミャンマー産陶器、鉛同位体比分析、N領域、ボーサイン鉱山、ソントー鉱山 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 論文 |
| タイトル | 籾の貯蔵・脱穀・脱稃方法にみられる穂摘み頴稲と高刈り稲穀の間の違い:東南アジアの文化間比較に基づく民族誌モデルの提示 |
| 著者 | 小林 正史(北陸学院大学)、村上 由美子(京都大学) |
| 掲載ページ | 25-42 |
| 要旨 | 東南アジア民族誌において穂摘み頴稲の貯蔵、脱穀、脱稃の方法の特徴を明らかにするために、穂摘みと根刈りの民族誌を比べた。その結果、1 脱粒しにくい米品種を多用する島嶼部の伝統的水田稲作では「穂摘みした頴稲を高床倉庫に貯蔵し、随時取り出して臼杵による脱穀、脱稃・精米を連続して行う」、2 穂からの脱粒性が極めて高く、登熟時期が不揃いな品種を多用する山地焼畑民では「穂摘みした頴稲をその場で踏みつけ法か叩きつけ法で脱穀し、稲穀(殻つき籾)で貯蔵する」、3 他の多くの高刈り・根刈り例では、登熟時期が斉一的で比較的脱粒しやすい品種を用いるため「収穫直後に全ての稲を踏みつけ法か叩きつけ法で脱穀し、稲穀で貯蔵する」という、米品種の特徴に応じた違いがみられた。 |
| キーワード | 穂摘み、高刈り、頴稲、脱穀、脱稃、臼杵 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 論文 |
| タイトル | 台湾考古学における外部的影響と内部的発展をどのように考えるか?-鹿野忠雄「原ドンソン文化」と三和文化を事例として- |
| 著者 | 俵 寛司(国立台湾大学) |
| 掲載ページ | 43-58 |
| 要旨 | 本稿では、かつて鹿野忠雄(1906-1945)により台湾先史時代の文化層の一つとして提唱された「原ドンソン文化」("Proto Dongsonian Culture")に関する学史的検討と、台湾東部先史時代の考古学的文化である三和文化および三和文化中期(1980BP-1420BP)とされる台東県金崙遺跡の発掘成果を事例として、台湾考古学における外部的影響と内部的発展をどのように考えるかについて論じる。 |
| キーワード | 鹿野忠雄、原ドンソン文化、三和文化、台湾考古学、外部的影響/内部的発展 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 研究ノート |
| タイトル | ジャヤヴァルマン7世期における統合のイデオロギー-観音像と「仏の花飾り」- |
| 著者 | 宮﨑 晶子(茨城キリスト教大学) |
| 掲載ページ | 61-71 |
| 要旨 | 本稿は「毛孔に天人をあまた宿す」観音像に焦点を当て、ジャヤヴァルマン7世期における統合のイデオロギーを明らかにすることを目的とする。筆者の調査から、本像は領域の中央のみならず周縁からも発見されることが分かっている。このことから、本像はアンコールにおいて統合の役割を担っていたと考えられる。本像の典拠は『カーランダヴューハ』第2部第2章「毛孔の描写」であり、本章は『華厳経』の影響を受けている。『華厳経』のメインテーマは「相即相入(anyona-samavasaraQa, interpenetration)」、「包摂(samavasaraQa, gathering of all)」である。観音はアンコールにおいて、矛盾や衝突のない統合体としての融合を説いている。 |
| キーワード | 『カーランダヴューハ』、『華厳経』、「入法界品」、観音、統合 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 研究ノート |
| タイトル | 近現代の琉球諸島および台湾におけるセメント瓦 |
| 著者 | 波多野 想(琉球大学)、山極 海嗣(琉球大学)、武島 早希(琉球大学) |
| 掲載ページ | 73-84 |
| 要旨 | 近現代琉球諸島及び台湾の景観を特徴づける要素のひとつにセメント瓦がある。セメント瓦は、日本では明治末期から大正初期にかけて発祥したとされ、その後に植民地下の台湾に技術移転された。さらに台湾から沖縄本島に伝播した後、琉球諸島全域へと波及し、各地の瓦工場がそれぞれに個性的な装飾を備えた瓦を生産した。すなわち、セメント瓦は、近現代の琉球諸島及び台湾におけるモノの生産・技術・流通等を読み解くための有効な資料のひとつといえる。そこで本稿は、近現代の琉球諸島および台湾において、物質文化が伝播・進化するメカニズムの一端を解明するうえで顕著な事例としてセメント瓦があることを示し、その歴史的実態について整理する。 |
| キーワード | セメント瓦、島嶼研究、琉球諸島、台湾、物質文化 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 調査速報 |
| タイトル | 宮古島クバカ城跡 調査概報 |
| 著者 | 石井 龍太(城西大学)、本村 麻里衣(アーキジオ)、阿部 常樹(国学院大学)、角道 亮介(駒澤大学)、深山 絵実梨(立教大学)、高橋 怜土(国学院大学) |
| 掲載ページ | 87-91 |
| 要旨 | 本稿の執筆者の一人である石井は、元々琉球諸島の近世集落に関心を寄せ各地で学術発掘調査を実施してきた。そして近世琉球期に先行するグスク時代の集落遺跡との関係を考古学的に明らかにする必要性、また沖縄島中心の政治史的な琉球国史から距離を置き、先島諸島と民衆を含めた琉球史として捉え直す必要性を考えるに至った。宮古島には石積みを伴う特色ある遺跡群が分布する。いわゆる「グスク」の地域例として捉えられてきたものの諸点で異なり、この問題提起に大いに資すると期待されよう。具体的な調査対象として、宮古島南部に位置するクバカ城跡(図1)を取り上げた。近世琉球期の文献資料にも登場し、宮古島の同種の遺跡のうち、石積みがほぼ全周保存された貴重な事例である。現在は宮古島市の指定文化財となっている。本稿は2022年5月に実施したクバカ城跡の第1次調査について述べるものである。 |
| キーワード | 宮古島、グスク時代、石積み、城跡、集落跡 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 展望 |
| タイトル | 東南アジアの古代都市遺跡についての、私の疑問 |
| 著者 | 上野 邦一(奈良女子大学) |
| 掲載ページ | 95-98 |
| 要旨 | 昨年、東南アジア考古学会の年度大会の際、研究大会を持った。研究大会に参加できなかった私は、後日、発表者に当日の発表資料を送って貰った。なぜ、そのような依頼をしたかと言うと、東南アジアで発見されている古代都市についていくつかの疑問があり、その解明の糸口を得たいと思ったからである。私の疑問は主に3点である。1)アンコール・ボレイとオケオの関係、2)イーシャナプラほか、いくつかの都市の形状、3)都市内の核となる施設。これらの疑問は解決していないが、若い研究者が将来、私の疑問を解明することを期待して、書きとどめることにしたのが、本拙稿である。 |
| キーワード | 古代都市、東南アジア、都市の形状、都市の中心区画 |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 書評 |
| タイトル | 『A History of Maritime Trade in Northern Vietnam, 12th to 18th Centuries: Archaeological Investigations in Vandon and Phohien』Yuriko Kikuchi 著、2021年 |
| 著者 | 田畑 幸嗣(早稲田大学) |
| 掲載ページ | 101-102 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 書評 |
| タイトル | 『アジアの博物館と人材教育-東南アジアと日中韓の現状と展望』山形 眞理子・德澤 啓一 編著、2022年 |
| 著者 | 杉山 洋(龍谷大学) |
| 掲載ページ | 103-105 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | 書評 |
| タイトル | 『図説 世界の水中遺跡』木村 淳・小野 林太郎 編著、2022年 |
| 著者 | 野上 建紀(長崎大学) |
| 掲載ページ | 106-108 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | マングローブ通信 |
| タイトル | 台湾研究滞在記(2021年8月~2022年7月) |
| 著者 | 俵 寛司(国立台湾大学) |
| 掲載ページ | 109-110 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | マングローブ通信 |
| タイトル | 追悼 日越共同考古学調査の懸け橋―ハン・ヴァン・カン教授 |
| 著者 | 菊池 誠一(昭和女子大学) |
| 掲載ページ | 111-112 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |
| 種別 | マングローブ通信 |
| タイトル | 追悼 チャンパー、扶南考古学の開拓者―ルオン・ニン教授 |
| 著者 | 菊池 誠一(昭和女子大学) |
| 掲載ページ | 113-115 |
| 要旨 | - |
| キーワード | - |
| 掲載言語 | 日本語 |